紙面を埋め尽くす写真やイラスト、そして著名人たちの文章――それらは読者になにを見せ、代わりになにを死角へと隠したのか。多分にプロパガンダ的性格も備えたPictorial History of the Warのページをめくっていると、そんな疑問が頭に浮かんでくる。 1940年にジョージ・オーウェルは「右であれ左であれ、わが祖国」と唱えたが、この刊行物が克明に記録するのは、さまざまな左右の政治勢力が、打倒枢軸国という共通の旗の下にとりあえず同居する様子である(まさしく「呉越同舟」のように)。 目次をめくると、当然のように戦争指導者ウィンストン・チャーチルの名前が頻繁に目に飛び込んでくるが、13巻にはのちに彼から首相の座を奪う労働党のクレメント・アトリーの記事があるし、その前後からはルーズベルトやスターリンの名前もたびたび登場している。 著名な労働党系知識人ジョン・ストレイチー(かつて夭逝したマルクス主義批評家クリストファー・コードウェルの遺稿集に序文を寄せたこともある)が、戦争中には“Squadron-Leader”の肩書でイギリス空軍の広報を担当していたことが分かるのも興味深い(例えば、24巻以降の記事を参照)。 表面的には団結していたこうした人々のメッセージのあいだに、見えざる断層は走ってはいなかったのか。あるいは、彼の記事を飾る爆撃機や巨大な12,000ポンド爆弾の写真は、遂行中の戦争を生々しく示してくれると同時に、片やそれがどれほどの破壊の渦をドイツの各都市に巻き起こしたのかは、想像力をもちいてW・G・ゼーバルトのいう、まさに書かれざる「破壊の博物誌」を構想するほかはない。 こうした疑問から、歴史への想像力を大いに刺激してくれる今回の復刻版の刊行を歓迎したい。
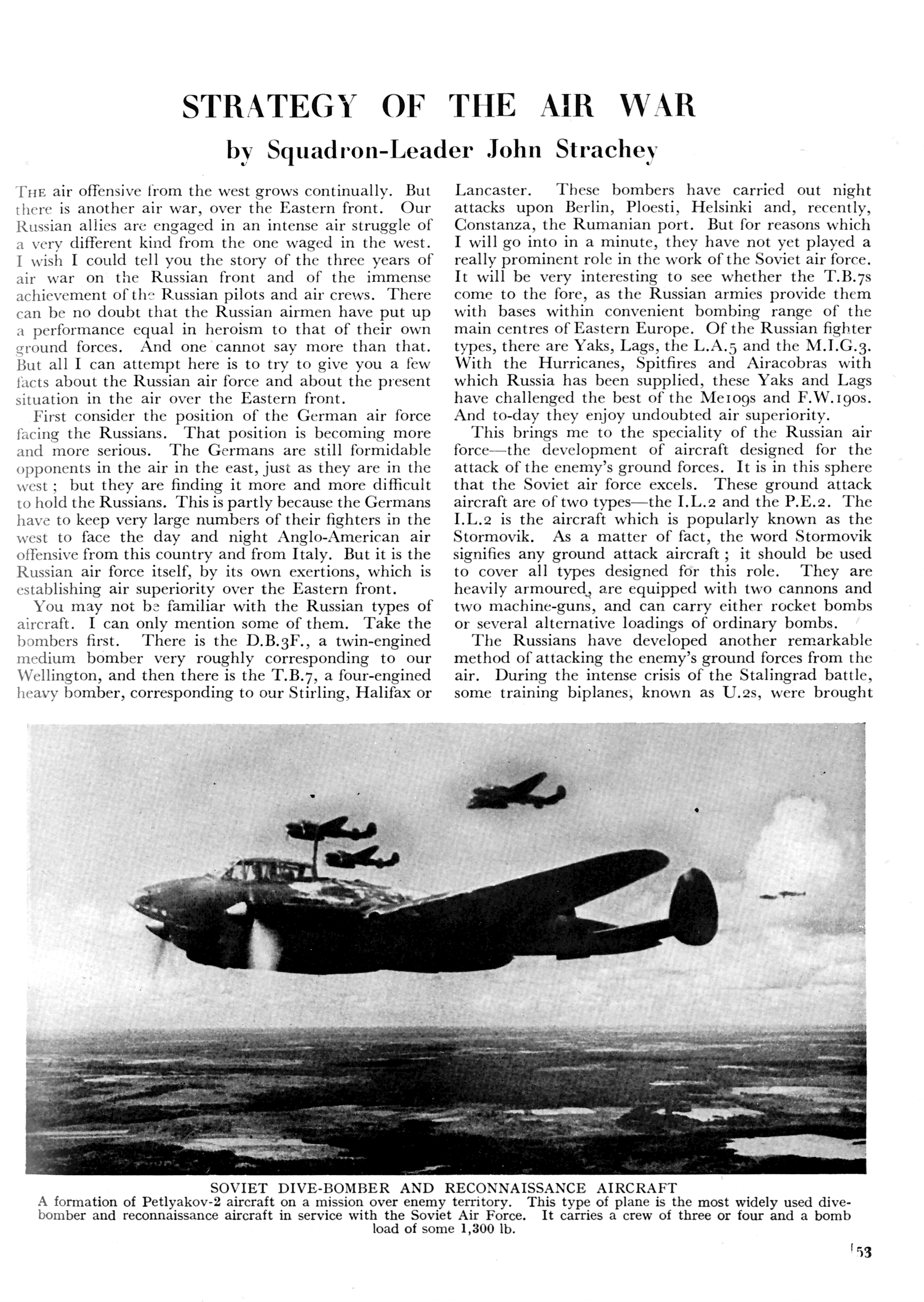 |
 |